船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ


〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は『心臓血管病と海藻摂取の関係』についてです。

海藻には豊富なビタミンやミネラル、食物繊維が含まれています。それぞれの成分は健康に良い、動脈硬化や心臓病に良い、と言われていますが、海藻自体が心臓血管病に効くのか、ということはよくわかっていません。
日本の多目的コホート(JPHC)研究で、筑波大学の研究チームが海藻摂取と脳卒中および虚血性心疾患リスクとの関連を調査・報告しました。
『Seaweed intake and risk of cardiovascular disease: the Japan Public Health Center–based Prospective (JPHC) Study』
研究対象は男性4万707人と女性4万5,406人で、約20年の経過を追っています。
海藻をほぼ毎日食べるグループとそうでないグループの2群に分け比較検討しています。
その結果、
男性では、海藻をほとんど摂取しない群に対して、ほぼ毎日摂取する群では、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)の発症率がで76%に低下、心血管疾患全体では88%に低下していました。
女性では、虚血性心疾患の発症率は56%に低下、心血管疾患全体で89%にまで低下がみられました。
一方で海藻摂取と脳卒中の発症リスクには明らかな関連は認められなかったということです。
海藻摂取のパワーが明らかになりました。海藻にはビタミンやミネラルだけでなく、ポリフェノールも豊富です。そういったあらゆる栄養素の複合が心臓病の発症を抑えたと考えられます。
特に女性で虚血性心疾患の発症が56%にまで低下した事実は驚きです。
虚血性心疾患などの心臓病を予防するためにいたずらに薬をのんだりサプリメントに頼るのではなく、まずはこういった体に良い食事を欠かさないことから始めないといけませんね
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は、糖尿病性網膜症とEPA(魚の油)の関係についての論文をご紹介します。

糖尿病は、たくさんの合併症を抱えているという問題があります。
大きな血管が詰まる心筋梗塞などの心臓病や脳卒中。
小血管の動脈硬化や神経異常が関与して起こる症状に糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症があります。
普段から、糖尿病のコントロールをしっかり行うことがこれらの合併症の可能性を低くしてくれます。
今回、早期の糖尿病性網膜症に対してEPAが効く可能性があるという論文が発表されました。
『Omega-3 Fatty Acid and its Metabolite 18-HEPE Ameliorate Retinal Neuronal Cell Dysfunction by Enhancing Müller BDNF in Diabetic Retinopathy』
ラットを用いた実験を報告したこの論文によると、EPA(エイコサペンタエン酸)の内服で、網膜内の酸化ストレスが減少。それにより網膜内のBDNF(神経細胞の成長、維持や再生を促進するタンパク質神経細胞の成長、維持や再生を促進するタンパク質)が増加し、それに伴い糖尿病性網膜症の網膜内酸化ストレスが軽減、網膜内神経細胞であるAmacrine細胞障害が抑制された、ということです。
オメガ3の代表格であるEPAを投与することで、酸化ストレスが減り、糖尿病性網膜症のダメージを減らしてくれることが明らかになりました。
オメガ3は糖尿病性網膜症に関わらず、心臓血管病などの動脈硬化に良いと言われています。
これからもオメガ3がたくさん含まれた食品をしっかりとって、体の酸化を防いでいきましょうね
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日のテーマは、『重症低血糖と認知機能低下リスク』です。

今回、高齢の1型糖尿病の患者さんを対象に、重症低血糖と認知機能低下リスクに関する論文が発表されましたので、シェアいたします。
対象は高齢1型糖尿病患者さん718人。平均年齢は67歳。
重症低血糖は自己申告、または低血糖で病院を受診・入院を要したもの、としています。
認知機能は、全般的認知機能のほか、言語能力、実行機能、エピソード記憶、単純な注意力を評価。
結果は以下のとおりです。
解析対象の50%は少なくとも1回の重症低血糖の既往があり、32%は過去12カ月以内に重症低血糖を経験していました。過去12カ月以内の重症低血糖を経験したグループでは、全般的認知機能の低下リスクが3.22倍上昇していました。
また特異的認知機能のうち、言語能力や実行機能、エピソード記憶との有意な関連も認められました。
高齢の糖尿病患者さんにおいて、あらためて低血糖予防の重要性が明らかになりました。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は、『心筋梗塞の再発と肥満の関連』についてお話します。

そもそも、肥満といえばメタボリックシンドロームですよね。メタボは肥満に加えて高血糖や中性脂肪、高血圧など動脈硬化の因子を複数抱えている人たちのことです。
これらの人が心筋梗塞などの心臓血管病のリスクが高いことはよく知られています。
一方で、心筋梗塞を起こした人が肥満だった場合の再発リスクに関してははっきりとしたことはまだわかっていません。
カロリンスカ大学病院(スウェーデン)の研究者らがこの度、腹部肥満を抱えている方に心筋梗塞の再発多いというデータを発表しました。
『Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction』
この研究は心筋梗塞をおこした約2万人を対象に行われ、追跡期間は3.8年でした。
腹部肥満の定義は男性でウエスト94cm以上、女性で80cm以上と定義されました。
その結果、腹部肥満があると心筋梗塞や脳卒中などの再発率が高いことが判明したのです。
また、このリスクは男性の方で高かったということです。
今後は、心筋梗塞を起こした肥満者が体重を落とすことで心筋梗塞の再発率を下げられるのか?にも注目したいですね。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は、『糖尿病の微小血管の合併症が歯周病治療で減少する』というレポートをシェアします。

糖尿病の3大合併症があります。糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症です。
これらはいずれも糖尿病に伴う微小血管障害が原因の一つとなっています。
これらの合併症を抑えることは、糖尿病患者さんのADLを大きく左右します。
これらの合併症が歯周病をコントロールすることで低下させられるという論文が米ハーバード大学歯学部のSung Eun Choi氏らから「Diabetes Care」誌に報告されました。
『Impact of Treating Oral Disease on Preventing Vascular Diseases: A Model-Based Cost-effectiveness Analysis of Periodontal Treatment Among Patients With Type 2 Diabetes』
この報告によると、歯周病治療の効果としての糖尿病性微小血管症は、糖尿病性腎症が20.5%、糖尿病性神経障害が17.7%、糖尿病性網膜症が19.2%抑制されるという結果でした。
もし、糖尿病を患っているのならぜひ歯周病のケアに目を向ける必要がありますね。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は、『深部静脈血栓症と塞栓症のリスク』についてお話します。
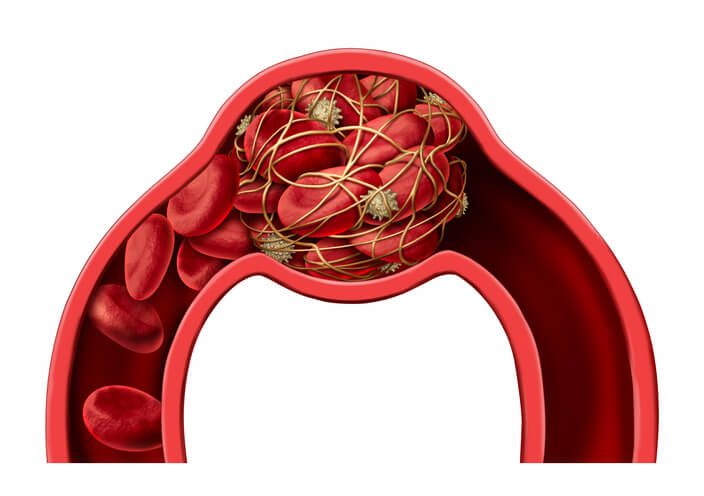
当院は、内科・循環器内科・心臓・糖尿を中心に診療しています。
その中で、血管のつまり、深部静脈血栓症(DVT)の方も多くいらっしゃいます。
深部静脈血栓症は、肺塞栓症などの血栓塞栓症が最も危険な合併症の一つと言われています。
今回ご紹介する論文では、肥満や高血圧・脂質異常症・高血糖・糖尿病などの生活習慣病、動脈硬化の危険因子を持っていると静脈血栓塞栓症が起こりやすいという結果を得ています。
『Metabolic syndrome increases risk of venous thromboembolism recurrence after acute deep vein thrombosis』
静脈血栓塞栓症の再発率は、リスク因子がまったくない患者では7%、リスク因子が1つの患者では14%、2つの患者では21%、3つの患者では30%であり、4つを保有する患者では37%に達していたのです。
つまり、メタボリックシンドロームの要素をたくさん持っていると、深部静脈血栓症後の血栓塞栓症の危険性、肺塞栓症の危険性が高まるということです。
一方でワーファリンやDOACと呼ばれる抗凝固薬を内服していた人には血栓塞栓のリスク上昇は見られなかったそうです。
深部静脈血栓症(DVT)を起こしたら、メタボリックシンドロームの要素を一つでも減らす努力が必要ですね。
それにはもちろんバランスの取れた食事や定期的な運動、十分な睡眠などが必要なのはいうまでもありません。
当院は心臓血管病、狭心症、心筋梗塞後などの循環器疾患や糖尿病、高血圧、コレステロール値異常などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日は、『糖尿病と超加工食品摂取量の関係』についての論文紹介です。

パリ大学(フランス)のBernard Srour氏らのグループにより、インスタント食品やスナック菓子などの「超加工食品」の摂取量が多いほど、糖尿病のリスクが高まるとする報告が「JAMA Internal Medicine」に掲載されました。
対象は約10万人のフランス人で、6年間追跡調査したところ、超加工食品の摂取量が10%増えるごとに糖尿病になる危険性が15%上昇するという関連が認められたのです。
超加工食品には人工甘味料や多くの保存料、添加物が使われていることが多く、インスタント食品や菓子パン、冷凍食品、チキンナゲットなどには多く含まれているようです。
今回の研究では、特に運動量が少ない人や肥満者、生活習慣病を抱えている人、また果物や野菜の摂取量が少ない人に超加工食品摂取が多い傾向があったとの報告もありました。
現代の生活で加工食品をなくすというのはほぼ不可能だと思います。
しかしながら糖尿病になると動脈硬化が進み、心筋梗塞や狭心症、脳卒中、閉塞性動脈硬化症、脳血管性認知症などあらゆる病気のリスクがとても高まります。
それを防ぐためにはしっかり運動をし、野菜を摂取し、そして超加工食品を減らすように食を選択する、ことが大切だということが改めてわかりますね。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
新型コロナウイルス感染がヒトーヒト感染が明らかになっている中、きょうは、新型コロナウイルスのヒトーヒト感染で親子間感染における症例の発表が有りましたので、シェアいたします。
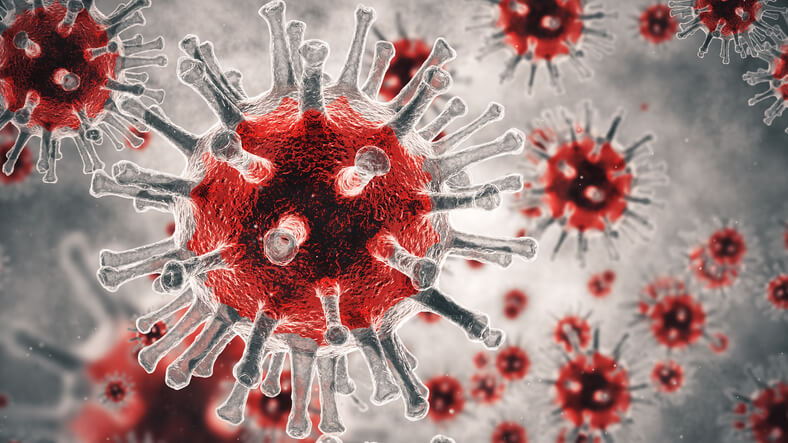
NEJM誌(ニューイングランドジャーナルオブメディスン)の発表です。
報告症例は、武漢市から旅行でホーチミン市を訪れていた中国人男性(65歳)とその家族についてです。
男性は1/13日に妻とベトナム入り
1/17日に現地に済む息子さんと合流 この日に男性が発熱
1/20日に息子さんが発熱 咳・嘔吐・下痢もあったようです。
1/22日 男性と息子さんが病院搬送 2人に新型コロナウイルスの陽性反応検出
男性は肺炎で一時呼吸困難示すも軽快 息子さんは肺炎症状はなく軽快 奥さんは発症せず
新型コロナウイルスが男性から息子さんに感染したと思われ、息子さんの発症までの潜伏期間は3日以下でした。
新型コロナウイルスは、エンベロープウイルスの一つす。エンベロープウイルスはアルコール消毒剤によりダメージを受けることがわかっています。アルコールがウイルスの膜を破壊するからです。
日頃のケアとして、アルコール消毒材によるこまめな手洗いを欠かさないことが大切です。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など
こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。
今日のテーマは『血管年齢とマラソン参加』についてです。

血管年齢とは、かんたんにいうと全身の動脈硬化度のことです。代表的なCAVIと言う検査機器などで動脈硬化度を測定し、その数値が年齢に照らし合わせたときに何歳くらいなのか?というものがわかる検査がります。
一度この検査をやられた方はわかると思いますが、血管年齢が実年齢より上だと結構ショックですよね。
血管年齢を下げるためには食事を改善しましょう、運動を定期的に行いましょう、というアドバイスはよく聞きます。
今回、トレーニングを行って初マラソンに参加することで血管年齢や血圧がさがったという論文がJACC「Journal of the American College of Cardiology」誌に掲載されました。
『Training for a First-Time Marathon Reverses Age-Related Aortic Stiffening』
この研究は、6ヶ月後の初マラソンを目指してトレーニングを行った健康な成人138人が対象です。
週に3回程度、1週間当たり6~13マイル(約10~21km)走るトレーニングを行い、トレーニング前と初マラソン完走2週間後でデータを比較しました。
すると、大動脈硬化度が9%改善しており、この結果は血管年齢が4歳若返ったことに相当したそうです。
考察では、目標を持って生活したことで運動が継続しただけではなく、食生活や睡眠にも良い影響を与えた可能性がある、と話しています。
健康になる、良いものを食べる、運動を欠かさない。こういった生活習慣の改善をしようと思ったときに、今回の論文のような『マラソンに参加する』などの具体的な目標をたててみると成功しやすいということですね。
もちろん、当院にはCAVIという血管年齢を測定できる検査機器をご用意しています。
CAVIに関しての詳しいサイトを載せておきますね
自分の血管が心配なかたはぜひ一度検査を受けられてください。
当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。
動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。
地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です
大穴中学校、県立千葉高校卒業
平成3年千葉大学医学部卒業
平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務
平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング
平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務
平成26年5月すぎおかクリニック開院
<取得資格>
医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など